「世界のボーディングスクール留学フェア(EMA)」開催報告
11月24日(月祝)にアメリカ、イギリス、スイス、タイなどのボーディングスクール約27校が参加して「世界のボーディングスクール留学フェア」(主催:EMA/SSAT)が開催されました。エディクムはグランドチームとして、事前準備から通訳の手配、事前説明会を担当しました。エディクムの卒業生が、各学校の通訳として、そしてボーディングスクール経験者として来場されたご家族と熱心に話している姿が見られた事を大変嬉しく思いました。
今年最大、そして年内最後の留学フェアを無事終了することができ、ご参加頂いた皆さまはもとより、ご協力頂いた方々に感謝申し上げます。
事前説明会では、ボーディングスクールの魅力や出願方法などをお伝えした後、エディクムの卒業生3名が留学前や留学中の体験談を披露しました。
参加して下さった皆様が、うなずきながら熱心にメモを取る姿も見られ、「生の声」を発信する事の大切さを改めて実感しています。
一部ではありますが、体験談を紹介させていただきます。
最初に自己紹介をお願いします。
K:小学校卒業後、ジュニアボーディングに入学し、高校、大学の合計11年間をアメリカで過ごしました。現在、国内大手飲料メーカーに勤務し6年目です。
R:2024年9月から日本の高校を1年間休学して、マサチューセッツ州のボーディングスクールで過ごしました。現在、日本の高校2年生です。
S:高校3年間をコロラド州のボーディングスクールで過ごした後、日本の国立大学を卒業。現在、テクノロジー系企業に勤務する傍ら、執筆活動を展開中です。
何故(日本ではなく)海外の学校へ進学しようと思ったのですか?
K:小学5年生の時に両親から日本の中学受験と海外留学の選択肢を与えられたのがきっかけです。当時は漠然と「英語を習得したい」「世界中に友人が欲しい」という比較的軽い気持ちで留学を選びました。もし合わなかったらいつでも帰国してよいという親からの強力なサポートがあったことが、決断を後押ししてくれました。
R:小学生の頃から海外旅行を通じて、外国の学校へ行ってみたい、という希望はありましたが、中学時代は実現できなかったので、高校生になって決断しました。
留学開始時の英語力はどの程度でしたか?
S:初回のTOEFLが20点台と悲惨でした。でもアメリカへ行きたい、何かを変えたい、という気持ちは凄く強かったので、留学先候補校の入学担当者と会った時は、相手の目を食い入るように見つめ、強い握力で握手をして、アピールしました(笑)。
K:“Hi, my name is K, please call me K.”ぐらいのレベルでした。しかし、現地での生活は英語が不可欠であるため、必死に勉強しました。約3年が経過した頃、英語のジョークを理解し、ジョークで返すことができた時に、言葉の壁を乗り越え、英語を話せるようになったと実感しました。環境と個人の努力が組み合わさって、能力は大きく伸びるのではないでしょうか。
R:留学を意識していたので、TOEFLやTOEFLジュニアは出願前から何度も受験しました。英語力は足りなかったと思いますが、入学したいという強い熱意を持ってインタビューに臨み、入学できました。
留学して良かったことは何ですか?最も印象深かったことや困ったことは?
R:困ったことは、感謝祭の休暇時に学校にホームステイ滞在を手配して貰いましたが、自分はフットボールをやっていてタンパク質の多い食事をしなければならなかったにも関わらず、滞在先の家庭がベジタリアンであったことです。
S:留学中に祖父母が相次いで逝去しました。最期に一緒にいられなかったことがとても心残りであり、改めて家族との関わりや絆の深さを実感しました。家族なのだから当たり前ではなく、自宅を離れてみて、または失ってみて改めてその存在の大きさや貴重さに気づきました。
K:リーダーシップをとる経験と様々なことに挑戦できる環境を得られたことです。失敗を恐れずに率先して行動する力が身に付きました。また意外な問題として、英語の習得を優先するなかで日本語に触れる機会が減り、一時的に日本語の語彙力や表現力が低下しました。親との会話や日本の書籍を読むことで、日本語の感覚を維持することに努めました。
3名の皆さんが共通して、留学を通して「自身の能力(キャパシティ)を正確に把握する力」と「自主的に助けを求める力」が身についたと話していました。自ら率先して行動する力はもちろん、困難な状況に直面した際に抱え込まず適切な相手に適切な支援を求めることができるようになったことは、社会に出てからも大いに役立っているそうです。3名の皆さんには、事前に「こちらからの問いに対し、好きなことを話してね。状況によっては参加者の皆さんからも質問を受けるかも知れません」と伝えてありました。どのような問いに対しても臨機応変、かつ自信をもって的確に答えている姿に、改めて感銘を受けました。





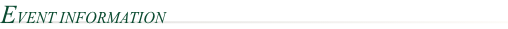 知る・触れる・イベント情報
知る・触れる・イベント情報

